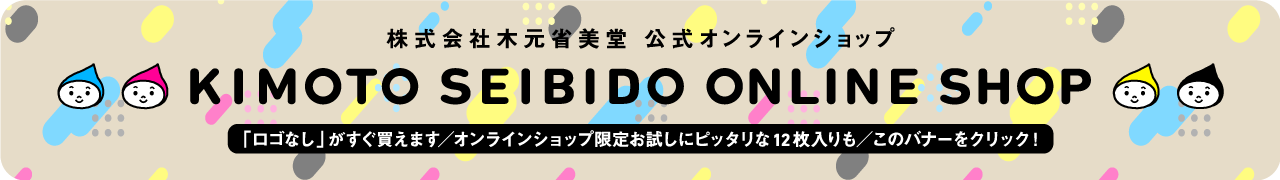伝トレカードの運用方法
組織での運用例
組織での一般的な運用例をご紹介します
簡単で親しみやすい運用方法で、組織のコミュニケーション活性化をサポートします。
伝トレカードは、各組織や企業のニーズに合わせて運用できます。
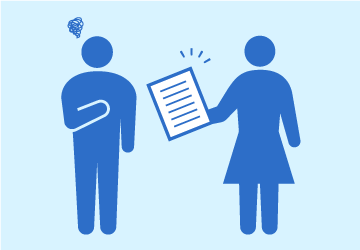
1.相手の良い行動に注目する
日常の業務の中で、上司や同僚、部下の良い行動に目を向けます。
困っていたときにサッと資料を渡してくれた、いつも元気なあいさつで気持ちがいい、部下への配慮がすばらしい…など、相手の良い行動に注目しましょう。

2.自由にメッセージを書く
感謝の気持ちや称賛の言葉を、カードに自由に記入します。
「Good Job!」または「Thank you!」のどちらの気持ちに近いのかチェックを入れ、日付、名前、メッセージを書きます。
文字だけでもいいですし、イラストを描いたり、シールを貼ってもいいかもしれません。気持ちをカタチにしましょう。

3.カードを手渡す
書き終わったカードは、相手に直接手渡します。
手渡しをすることで相手との距離が縮まります。
内容をその場で見られたくないときは表面を上にして渡しましょう。
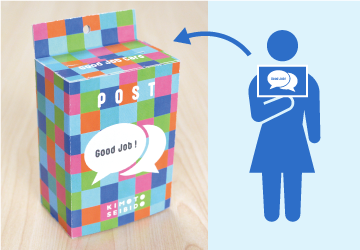
4.カードを読んだらポストに入れる
受け取った相手はカードを読んだ後、指定のポストにカードを入れます。
受け取った人がポストに入れます。
投函されたカードは、運営側が「月に一度」など回収頻度を決めて定期的に取り出します。

5.運営側がカードを集計し本人に返却
集めたカードは、運営側で集計し、本人に返却します。
運営側で配った人と枚数、受け取った人と枚数を集計し、受け取った本人に返却します。(月毎、四半期毎などあらかじめ集計頻度を決めておきましょう)
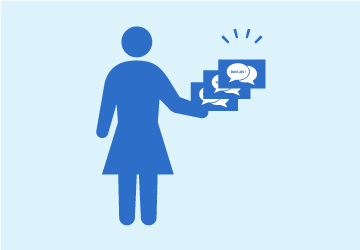
6.カードは個人で保管
返却されたカードは、各自で保管します。
うれしかったカードはメモスタンドで机に飾っても。
名刺サイズなので、名刺入れにも入ります。
カードを見返してモチベーションアップに繋げましょう!
運用アイテム
ポスト・賞状・褒賞品などのご相談も承ります。お問い合わせください。
ポスト
配布された枚数や受け取った枚数、誰が積極的に使用しているのかなど、効果測定をするためには運営側がカードを回収する必要があります。その場合は、社内にポストを設け、受け取った人に読んだカードを入れてもらいます。
ポストなら受け取った人はいつでも投函できますし、運営側以外の誰かに見られることはないので安心です。
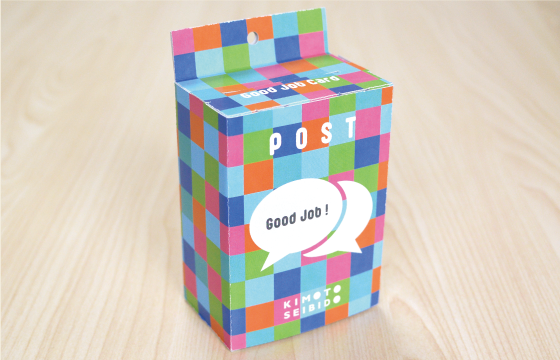
賞状
伝トレカードの活動を自然消滅させないためには定期的なアナウンスや表彰などによる動機付けが必要です。
そもそも伝トレカードは「カードを渡す」という行動を起こすことで相手との関わり方を自ら変えていくカードなので、カードをたくさん配布した人を称える賞があるとよいでしょう。
もちろん、良い行動をしてたくさんカードを受け取った人への賞も動機付けになります。
他には、運営側が最も印象深いエピソードを選ぶ「ベストエピソード賞」や、どのチームがたくさんカードを配布したかで贈る「チーム賞」など、自社に合った賞を作ると継続のモチベーションになります。

その他の褒賞品
褒賞品としては、身に付けられるピンバッジなどもよいでしょう。
もらった人は積極的に関わったことを認められた証として、もらっていない人には「目標」として、モチベーション向上に繋がるアイテムとなります。

より効果的に運用するために
運用前に「ねらい」「取り組み方」「ルール」の3つを決めておくことで、伝トレカードをより効果的に運用することができます。
この3つが決まったら運用開始前に周知しておきます。
ねらい
なぜ伝トレカード(Good Job Card)を導入するのか、どんな問題を改善したいのかを明確にしておきます。
(例)コミュニケーションの第一歩として、相手に興味を持ち、自分の思いを伝えられるようになってほしい場合
【ねらいの例】
自分以外の誰かに関心を持ち、良い部分を見つけ、相手に伝える習慣を身につける。
取り組み方を決める
「ねらい」に合わせて取り組み方を決めていきます。
(例)まずは積極的に使用することを促すとともに、運営側として配布枚数を把握し集計できるようにしたい。また、誰かに見られることが使用の障害になることは避けたいので、カードの掲示はしないこととする。
【取り組み方の例】
- 相手に伝えることをトレーニングするカードです。積極的に使用しましょう。
- 良い行動や感謝したいことをカードに記入し、相手に直接渡します。
- 受け取った人は読んだら回収ポストに入れてください。集計後返却します。
- 掲示はしません。素直な気持ちを書いて渡しましょう。
ルールを決める
ルールがあると使用することへのハードルが下がり、渡すことを後押ししてくれます。
【ルールの例】
- ルール1 書いていいのは肯定的な内容だけ。相手の良いところを見つけましょう。
- ルール2 受け取り拒否はできません。必ず受け取りましょう。
- ルール3 上下関係や役職を気にせず、良い行動や感謝したいことを書きましょう。
こんなときどうする?

直接渡せない場合は?
渡したい相手が外出中、勤務場所が違う、勤務時間が合わない…など、直接渡せない場合もあります。そんなときは、机の上に伏せておいたり、他の書類とともに運んでもらうなど、自分たちに合った運営方法を考えましょう。
木元省美堂の伝トレカードは表裏のあるデザインのため、表を上にしておけばメッセージが直接見られることもなく、安心して置いておけます。

部署間のコミュニケーションを改善したいときは?
部署ごとにカードの色を変えてみましょう。カードの色で他部署の人とどれだけ関われているかが一目でわかります。もらったカードが同じ色ばかりの場合、決まった部署の人だけとの関わりになっているということに気づきます。

活動を自然消滅させないためには?
集計結果だけでなく、名前を伏せて「こんなカードがありました」と内容を報告するなど、定期的にアナウンスしていくのが効果的です。また、配布枚数や受け取り枚数を表彰するなど、定期的に動機付けを行いましょう。